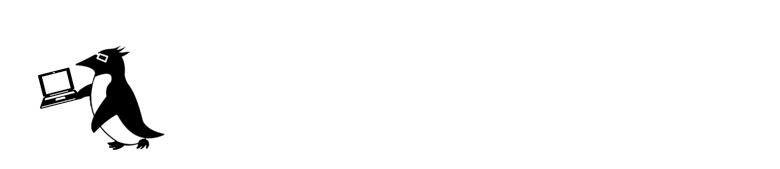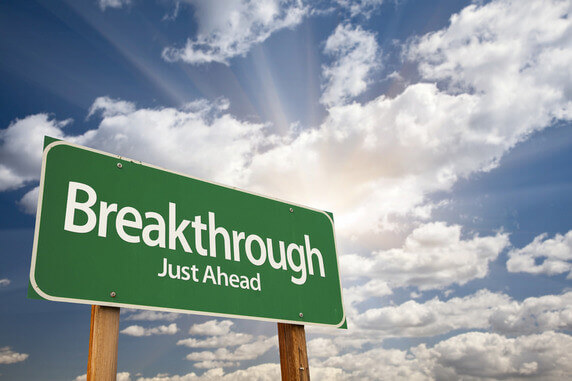どうも、マクリン(@Maku_ring)です。
営業からすこし離れた今でも、営業マンから相談を受ける機会がわりと多いです。
相談ごとで一番多いのがこちら。
 同僚
同僚
その上で採用にこぎつけるのが難しいと考えている理由をいくつか挙げてこられます。
ときに自分の価値観でがんじがらめになってしまうと、攻め手がないように思い込んでしまうものです。また、経験の長い人ほど固定観念にとらわれる傾向があります。
そんなわけで今回の記事は「売れない状況を動かすために、売れる営業マンが行う採用決定者の見極めとは?」です。
 嫌い・苦手なお客様から好かれる営業マンになるコツと4つのタイプ分け
嫌い・苦手なお客様から好かれる営業マンになるコツと4つのタイプ分け 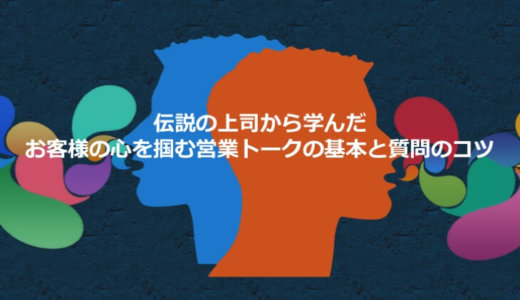 伝説の上司から学んだ、お客様の心を掴む営業トークの基本と質問のコツ
伝説の上司から学んだ、お客様の心を掴む営業トークの基本と質問のコツ  売上目標が上がり続けても、毎年必ず達成する営業マンが心がける3つのこと
売上目標が上がり続けても、毎年必ず達成する営業マンが心がける3つのこと 売れない状況を動かすために、売れる営業マンが行う採用決定者の見極めとは?
採用のコツは、基本的には採用決定権のある権限者を見極めることです。
絶対的な権限者が一人だけで決めている場合、その人に会って落とすだけ(簡単ではありませんが)で即採用につながります。
 マクリン
マクリン
大事なのは「そうでない先にぶち当たったとき、どういう行動をとるべきか分かっていること」です。
これを分かっているかどうかが、営業活動の質を決める大きな要素につながってきます。
まずは「この会社の権限者がどういう構成なのか」を把握する必要があります。
大きく分けると次の3パターンです。
- 複数の権限者がいる
- 権限者がいない(ように見える)
- そもそも無関心である
それぞれの攻略方法を紹介していきます。
Sponsored Links
1. 複数の権限者がいる
このパターンは結構多いです。
 マクリン
マクリン
採用まで時間がかかる分、そうそう簡単に他社には切り替わらないです。
ちなみに絶対的な権限者が一人で決めている先は、採用になるときも他社に変わるときも、時間がかからないものです……。
複数の権限者がいる先への基本攻略方針は、「各権限者に情報共有しながら、一人ずつ着実に落としていくこと」です。
例えば、A・B・C・Dという4人の権限者がいたとします。
Aが製品について考えていることを他の3人に伝達し、Aには他の3人が考えていることをフィードバックするのです。
そしてCが「この製品使ってみたいけど、私だけじゃ決められない」と言ったら、すかさず他の3人に共有し、4人の気持ちを一気にCと同じ方向へ合わせにかかるのです。
 マクリン
マクリン
そういう場合は、他の手を組み合わせてみましょう。
4人を一堂に集められる場合は、4人が意思決定できる場を作るのもいいです。たとえば説明会とか。
あるいは4人の力は均等とはかぎりません。というか、均等でない場合のほうが多いです。
4人の中でいちばん発言力のある人に「インフルエンサー」となってもらうのです。
インフルエンサーから他の3人に採用に向けた働きかけをしてもらい、4人の意思を統一しにかかるのです。
この場合インフルエンサー以外の3人には、それほど面会しなくても済みます。
中には、きっちり会って話をしないとヘソを曲げる人もいるので、その人の特性をよく見る必要はあります。
ちなみにこの「インフルエンサーを活用する」手法はけっこう使えます。
必ずしも権限者をインフルエンサーにする必要はありません。
例えばなかなか権限者に会えない場合、権限者と接する頻度の高い人をインフルエンサーに設定します。
その人から権限者に働きかけてもらうことで、攻略の糸口を作るというパターンもあります。
Sponsored Links
2. 権限者がいない(ように見える)
このパターンは一般的に攻略が難しいといわれています。
 マクリン
マクリン
僕なら諦める前にまず本当に権限者がいないかどうか、しらみつぶしに当たります。権限者がいないように見えるだけで、本当は見つけられていないだけもしれないからです。
前任者からの情報はその人の主観でもあるわけです。どれだけ優秀な前任者であっても。
 マクリン
マクリン
僕はけっこうあります。
ですが、ゼロベースで再調査した上でも「本当に権限者いないかも……」という会社はあると思います。
権限者不在パターンです。
こういうときは「問題意識を持っている人を権限者に育て上げる」ことを目指します。
現在の状況に問題意識をもっているかどうかは、こちらの記事でも触れた「What・Why・Howの質問」で浮き彫りにしていきます。
- お客さんの抱えている問題はなにか?(What)
- お客さんはなぜ、それを問題だと考えているのか?(Why)
- どうすればその問題は改善するのか?(How)
そして、問題意識をもっているお客さんを見つけたら、すかさず同調して寄り添います。
 マクリン
マクリン
僕は上記セリフをアレンジしてよく使っていました。
お客さんから「共通認識を持つ共同体」と感じていただくことが重要です。
それから具体的なアクションへ移れるように働きかけていくのです。
 マクリン
マクリン
いろいろな部署へ掛け合ってその都度フィードバックしていくうちに、○○さん自身がだんだんと権限者に近い存在に育っていきます。
あるいはその人自身が権限者に育たなくても、いろいろな部署へ掛け合っていくうちに数の力学で状況が動いていくこともあります。
最初はなかなか状況が動かないかもしれません。問題意識をもっている人すら見つからないこともあります。
そういう場合でも根気強く調査し続けることで、ふとした拍子にそういう人物は現れます。
権限者不在パターンでの成功体験は、営業マンにとって最大の自信と経験値になるものです。
そういう先を見つけてもすぐにあきらめることはせず、今後の自分のためにもチャレンジすることをおすすめします。
Sponsored Links
3. そもそも無関心なときはどうすればいいのか?
 マクリン
マクリン
このパターンもかなり多いです。ですが、こういう状況を動かしてこそ営業の醍醐味。
たとえば面会者Eから「■■(商品のカテゴリ)なんてどれも一緒じゃん」と云われたとします。
 マクリン
マクリン
まずはEさんの発言に同調して相手の見解を尊重します。
Eさんいわく、■■の中身(性能)はどれも似たようなものだから変える必要はないと思っているわけです。
つまり営業マンは、Eさんにとって「変えるに値する必要性」を見つけなくてはなりません。
そのためにはEさんの状況をひたすら聞いて、その中に我々が改善できる問題や状態がないか探っていくです。
改善できる問題や状態を探ったうえで、結局のところコストに行き着いたとします。
経営層ほど「コストダウンにしか興味ありません!」というのは多いものです。この「コストダウン」という言葉が要注意で、製品コストだけで考えがちなのです。
そして安易にそのキーワードに飛びついて、「今使っていらっしゃる製品よりも、うちの製品をぜったいに安くするので買ってください」と言ってしまう営業マンが多いのです。
ここで重要なのは、製品自体のコストで語るのではなく、「その製品を使うことによってどのようにコストダウンできるのか」を大きい視野で述べるのです。
簡単な例だと、「当社の製品を使っていただくことで、○○の使用量をこれだけ減らせるというデータがあります」などです。
すなわち製品が周辺に与える影響で話すよう心がけることです。
その上で「今使っていらっしゃる製品ですと、これだけの金額を無駄にしてしまうことにつながります」といった言葉を添えて現状から変えないことによってどうなるのかを伝達することで、切り替えの必要性に気付いてもらうのです。
 マクリン
マクリン
お客さんの状況をヒアリングして、自分の身に置き換えながら提案していくことが大事です。
Sponsored Links
まとめ
今回の記事は「売れない状況を動かすために、売れる営業マンが行う採用権限者の見極めとは?」について書きました。
無関心パターンからの動かし方は、記事中に書いた王道以外に「邪道パターン」もあります。
それはずばり「製品に関心を持ってもらえないなら、営業マン自身に関心を持ってもらおう」です。
振り返れば僕もいろいろやりました。
- 面会者の好きなお菓子をたくさん貢ぐ
- 面会者の娘さん息子さんの宿題を解いてあげる
- 面会者(女性)に男性を紹介する
ここまでやる必要はないですが、注文ゲットにこだわるなら、ときにこの手段も有効です。
営業に正解はありませんから。
どうも、マクリンでした。
 嫌い・苦手なお客様から好かれる営業マンになるコツと4つのタイプ分け
嫌い・苦手なお客様から好かれる営業マンになるコツと4つのタイプ分け 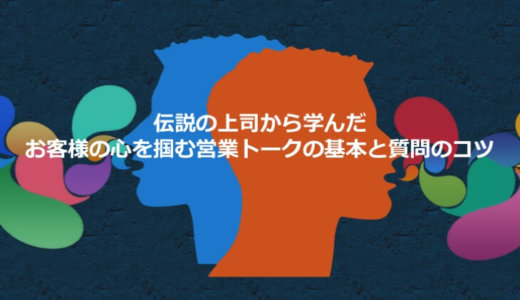 伝説の上司から学んだ、お客様の心を掴む営業トークの基本と質問のコツ
伝説の上司から学んだ、お客様の心を掴む営業トークの基本と質問のコツ  売上目標が上がり続けても、毎年必ず達成する営業マンが心がける3つのこと
売上目標が上がり続けても、毎年必ず達成する営業マンが心がける3つのこと